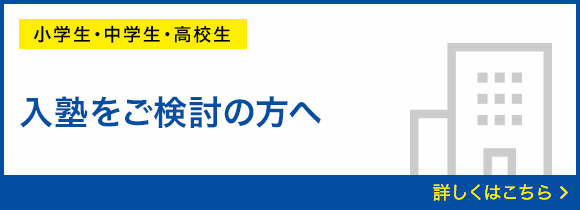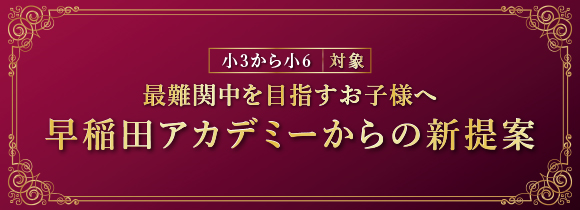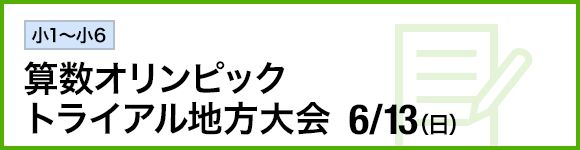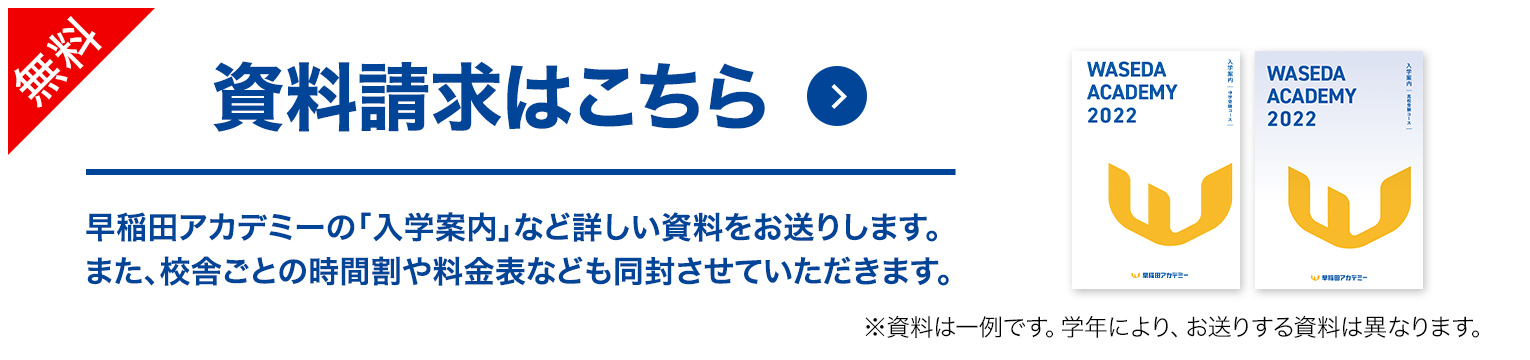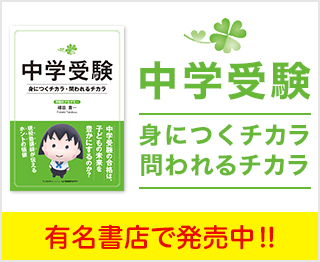『どこでつまずいているのか』
2025.03.14
小学5年生ぐらいになると、家庭学習の細かい内容について、保護者の皆様がご覧になったり、教えたりということは少なくなっていくはずです。しかし、低学年から中学年にかけては、お子様が質問してきたときに細かく見て教えることも多いと思います。今回は、お子様の家庭学習に関するアドバイスについて書かせていただきます。
次の問題をご覧ください。小学2年生の算数の問題です。
ひとつに3人が座れる長いすが6脚あります。 ①あつし君の班には15人の生徒がいます。全員が座ったとして、あと何人座れますか。 ②あつし君のクラスには全部で32人の生徒がいます。何人が座れなくなりますか。
さて、この問題についてお子様から質問されたとします。皆様はどのようにアドバイスをなさいますか。
多くの方が、まずご自身で解いてみて、解き方を理解(確認)したうえで、その方法をお子様にお伝えになるはずです。しかし、ここでもう一つ考えていただきたいことがあるのです。それは、お子様がどの部分でひっかかっているのか、ということです。どのように考えて、どの点でつまずいているのかという「お子様に対しての理解」というイメージです。
例に出した問題で考えてみます。これは「かけ算」の単元で出されている問題ですから、大人が普通に考えれば簡単に解けてしまいます。
①3×6-15=3 答え(3人) ②32-3×6=14 答え(14人)
となります。さて、それではお子様はどの部分でつまずいてしまうのでしょうか。
まず考えられるのが、「『全体』を考えることができていない」ケースです。この問題は、式でいえば「3×6」の部分にあたる「全体」を最初に考えるべきです。もし学校の教科書にこの問題が載っているとしたら、①の問題の前に、『長いす全部では何人座れるでしょう』という問題があることでしょう。そこで出てきた「18人」という数字をもとにして、次の小問を考えていくわけですが、その点に気付くことができずにつまずいてしまうわけです。
次に、「全体で18人座れる」ということはわかったが、「どちらからどちらをひけばよいのか」がはっきりわからない、というケースも考えられます。小学校の算数では負の数の概念を学んでいないため、引き算は「大きい数から小さい数を引く」というのが大原則になります。ところが、そのイメージに引っ張られて「引く数」と「引かれる数」があいまいになってしまい、その引き算の答えが何を意味しているのかがわからなくなってしまうことが多々あります。
少し細かく算数の問題について触れてしまいましたが、おわかりいただけたでしょうか。「教えるということ」について、私が職員(講師)に研修をする際には、「教える問題に対する理解」だけではなく、「教わる生徒に対する理解」が重要だと伝えています。単に問題の内容や解き方を研究するだけではなく、それ以上に教わるお子様がどのような状況にあるか、を把握することが大切なことだと、私は考えています。
- 2025.03.14 『どこでつまずいているのか』
- 2025.03.12 『集中力が続かない……』
- 2025.03.07 『読解力が国語の基盤』
- 2025.03.05 『3月、新しい気持ちで……』
- 2025.02.28 『テストに真剣に取り組む』