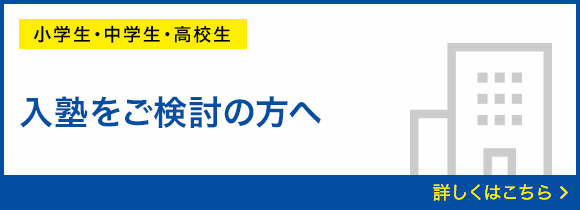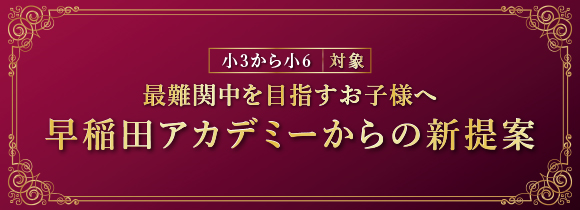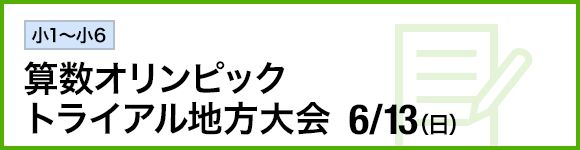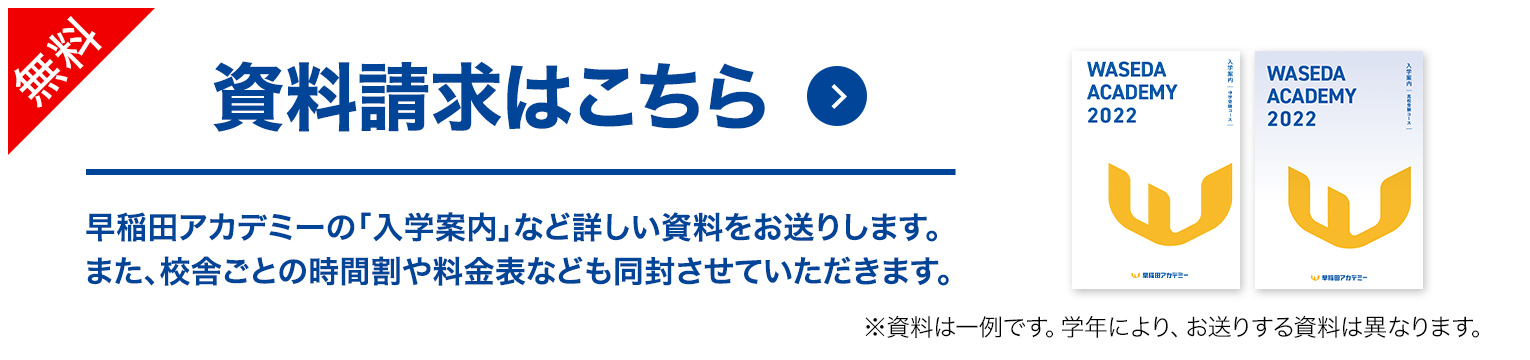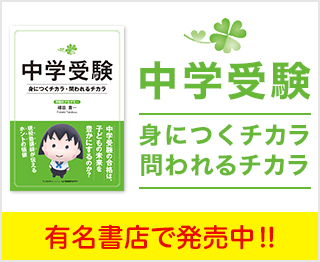『よい質問、悪い質問』
2025.03.26
小学5年生の生徒が、算数の問題について質問にきました。「A店とB店では同じ品物を同じ個数仕入れました。A店では1個につき120円の利益が出るように定価をつけましたが、仕入れた個数の7割しか売れませんでしたので、残りは定価の2割引で売って、全体の利益は9600円になりました。B店では……」という「売買損益」の問題でした。「複雑な問題だから、まずは表に整理してみよう」と話し、表を書き始めたのですが、その瞬間「わかった!あとは自分でやってみる!」と、私が書いた紙を手に自習室に戻っていきました。その後音沙汰がないので、自習室を覗いて「さっきの問題は?」と尋ねたら、「できた!」と笑顔で返してくれました。
とてもよい「質問のしかた」……というよりも、よい「質問の聞き方」だと思いました。問題について、自分で真剣に考えてから質問にきたのでしょう。ただ、難度の高い問題でしたから、自分1人で考えているときにはどこから考え始めればよいのかが思いつかなかったのだと思います。解説を聞いているときに、頭を回転させているのがよくわかりました。
一方で「よくない質問のしかた・聞き方」というのもあり、意外に多くの小学生がそんな質問をしてきます。問題を読んで「なんだか難しそうだな」と思ったら、自分で真剣に考えることなく、質問することで安易に「解決」しようとしてしまうパターンです。そういった場合、私は次のように対応しています。 「質問はどこ?」 「この問題……」 「この問題のどこがわからないの?」 「う~ん……全部……」 「どんな問題だったか覚えている?」 「……わからない」 そんなやり取りになります。そして「もう一回ちゃんと考えてごらん。君だったらできる問題だよ。ヒントは……線分図!」という一言で自習室に行かせます。しばらくたって声をかけると、「線分図書いたら、できた」という答えが返ってくることが多くあります。
このような場合、残念ながら、質問にくる段階では「真剣」には考えてきていなかったのでしょう。そのような状態で質問に対して答えても、自分で解けるようにはならないはずです。先生が目の前で解いてくれるのを「なんとなく」見ているだけで終わってしまうことが多いものです。そういった質問を繰り返していると、「自分で解決する」のではなく、「誰かに解決してもらう」という学習スタイルを身につけてしまうことにもつながりかねません。
小学3年生・4年生の時点では、ご家庭でお父様やお母様に質問をすることも多いはずです。もちろんお教えいただくのは問題ありませんし、その場で解決してあげることが必要な問題(特に算数の計算系の問題など)もあるはずです。ただ、お父様やお母様が「代わりに解いてあげる」というような対応にならないように、ご留意いただければと思います。
- 2025.03.26 『よい質問、悪い質問』
- 2025.03.21 『春休みに成長をうながす』
- 2025.03.19 『休眠打破』
- 2025.03.14 『どこでつまずいているのか』
- 2025.03.12 『集中力が続かない……』