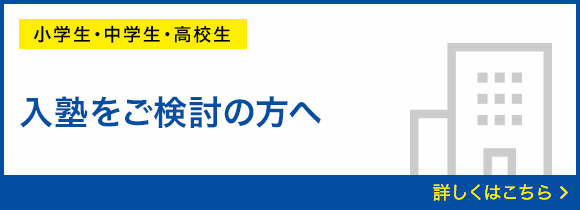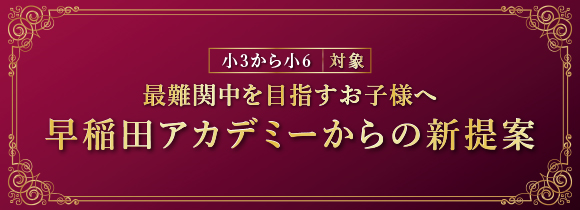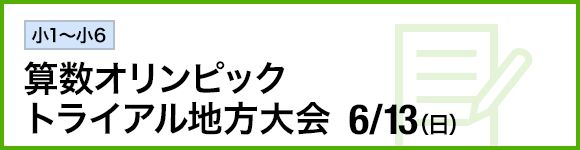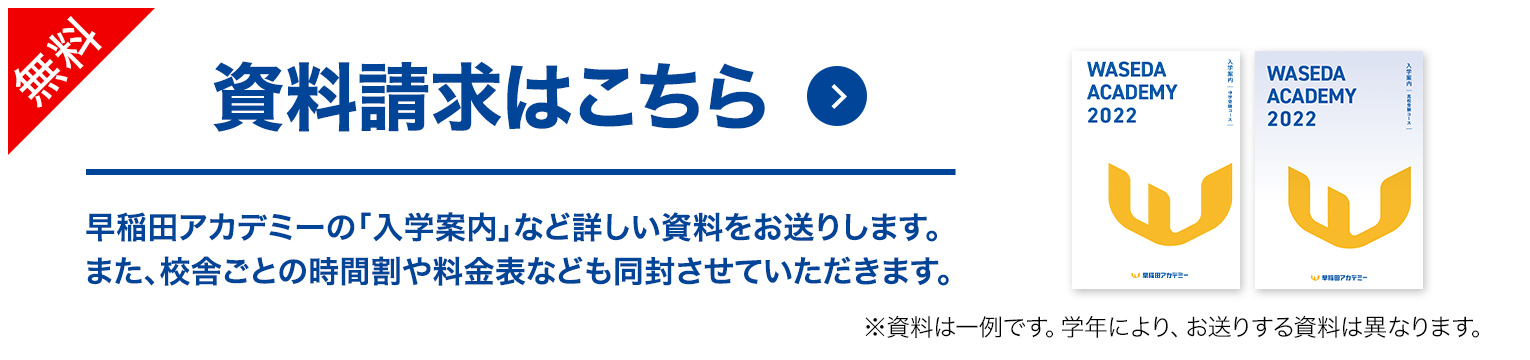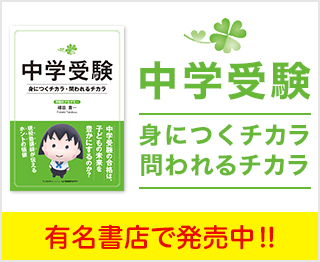『休眠打破』
2025.03.19
桜の季節が近付いています。コンビニエンスストアなどには、桜をテーマにしたスイーツやドリンクが店頭に並び始めています。桜のお菓子といえば、代表格は「桜餅」です。あまり和菓子を食べることはないのですが、「桜餅」は見かけると食べたくなります。あの桜の風味、意外と好きなのです。「桜の風味」と書かせていただきましたが、味ではなく匂いでしょうか。さて、桜が咲いたら、お子様方に桜の「花」の匂いをかがせてみてください。実は、桜の「花」には、匂いがほとんどないのです。あの「桜の風味(匂い)」は、桜の花の匂いではなく、葉の匂いです。「桜餅」も花の匂いを付けているわけではなく、桜の葉で巻いてあることから、あの風味になっているわけです。
テレビでも「開花予想」が話題になってきています。いくつかの予想・予報があるようですが、私が見た番組では、東京の開花予想日は「3月24日」となっていました。私の実家に大きな桜の木があるので、昨日見てみたのですが、日当たりのよい枝の蕾は膨らんできているようでした。先週から春めいた暖かい日も増えてきましたので、そろそろと思っていたのですが、まだすぐというわけにはいかなそうです。
さて、地球温暖化の影響もあり、「暖冬」といわれる年も増えています。暖かくなり始める時期が早くなると、桜の開花も早まると思ってしまいがちですが、実はそういうわけでもないことをご存じでしょうか。2020年に、東北地方での開花が九州地方よりも早かった、というニュースがありました。この現象は「東北地方の3月の気温が高かったから」起きたわけではありません。正しくは、「九州地方の真冬の気温が十分低くならなかったから」なのです。
桜の開花のメカニズムの中で大切なものに、「休眠」と「休眠打破」というものがあります。簡単に説明をすると、桜は夏に花芽をつくります。その芽が秋になると、冬の寒さを乗り越えるための「休眠」状態に入ります。そして、冬の寒さ(0度から10度)が一定期間続き、冬が来たことを感じると、「休眠」状態から目覚めるのです。これが「休眠打破」といわれるものです。桜の場合、「休眠打破」の時期は1月末から2月初旬くらいのようです。そして「休眠」から目覚めると、そこから先は暖かさによって成長スピードが変わるのです。ですから、冬にある程度の寒さが続かないと、「休眠打破」が遅れて、暖かくなってきても開花が遅くなることがあるわけです。地球温暖化がさらに進んでしまうと、桜の開花前線が「南から北」ではなく、「北から南」になってしまうのではないか、という話もあるようです。
この「休眠」のメカニズムは、桜だけではなく、さまざまな植物に共通するものなのですが、なんとなく人間にもあてはまるようにも思っています。大人でもありそうですが、特に中学受験へ向けて学習をしている小学生を見ていると感じることがあります。「この子はいま休眠状態だな」「ちょっと目覚めてきたかな、休眠打破だな」……そんなイメージです。この「休眠打破」のタイミングは、低学年から中学年の間は精神的な成長・発達による部分が大きいようです。よくいわれる「9歳の壁、10歳の壁」を越えてくると、学習面においても一段階成長してくるように感じています。そして、小学5年生から6年生にかけては、「受験生としての意識が芽生える」「志望校を明確に意識しはじめる」といった要素が、「休眠打破」を促す重要な要素になると思うのです。
「休眠打破」に必要な「寒さ」と、「目覚めてからの成長」を促すための「暖かさ」。そんなイメージを持って生徒に接していきたいと、いつも考えています。ご家庭でもイメージしていただければと思います。
- 2025.03.19 『休眠打破』
- 2025.03.14 『どこでつまずいているのか』
- 2025.03.12 『集中力が続かない……』
- 2025.03.07 『読解力が国語の基盤』
- 2025.03.05 『3月、新しい気持ちで……』